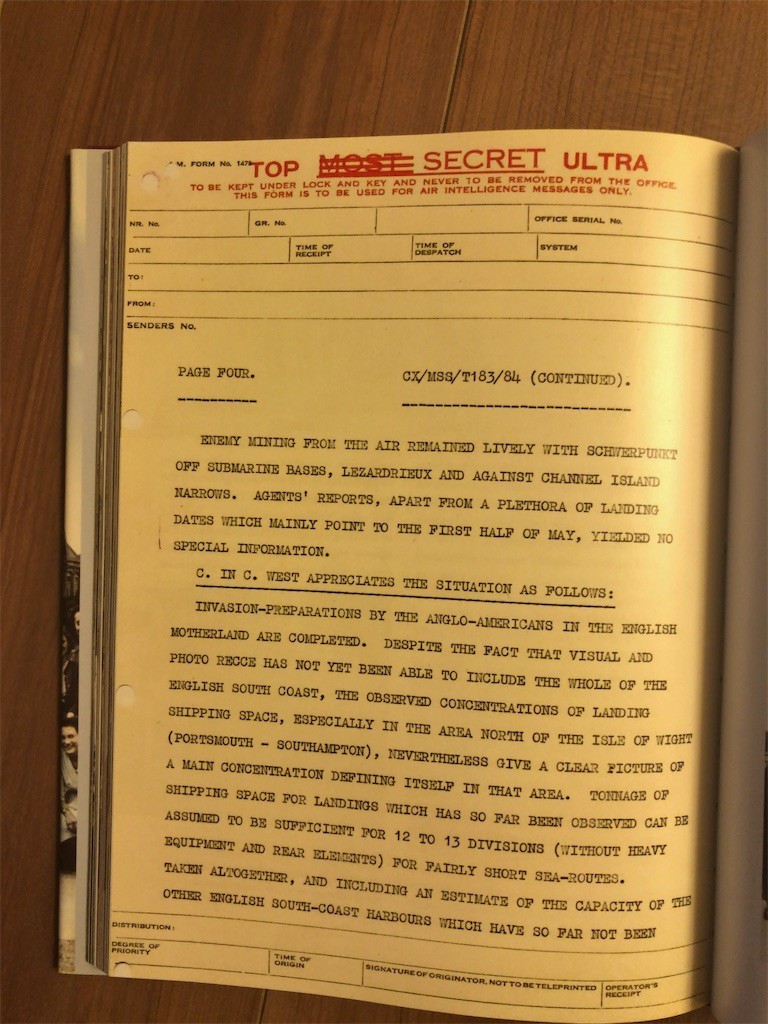クヌース先生の本を読む機会が増え、とはいうもののその内容を理解できる能力に欠けるので表面をなぞるくらいで精一杯なのだけれど、バックボーンとなっている知識の豊かさに触れられるのはありがたいことで、個人的に調べてみたいことをいくつも見つけている。その中の一つが、組版、タイプセッティングであるのは、クヌース先生を知っている人であればわかりやすい展開だろう。とはいえ、その内容は広範囲に及ぶ。そういえば、本そのものの歴史というのをきちんと追いかけてみたことがあるとはいえない。というわけで、本の歴史に関する本を読んでみた。
河出の『図説 本の歴史』は印刷博物館の人たちがまとめている日本から見た本の歴史という感じ。世界に広がる本のことを体系的に追いかけることができる。朝鮮半島では西洋の活版印刷に先立って金属活字の鋳造が行われていたとのこと。13世紀には利用されていたという。印刷博物館に複製があるということなので、次に行ったときに確認してみたい。どのようにリニューアルされるのか、そちらもずっと楽しみにしていたりする。
創元社の『本の歴史』はフランス語からの翻訳書。欧州を中心としたきれいな本を眺めているだけで楽しい。この本には資料編として荒俣宏による解説が加えられていたりする。イギリス人にとって本はゲストであるのに対して、フランス人にとって本は生涯の友であるという解説がとても興味深かった。フランス人には、「本は読むよりも前に買い集めるもの」なんだとか。イギリス好きな私だけれども、本に関してはフランス人の方が共感できることが多いのかもしれない。
私的にこの本のなかでいちばん気になったのは、「十二折り判」の存在だった。一折24ページという使い方があるのか。解説しているページを見つけたけれど、どのように折るのかもう少し調べてみたい雰囲気である。
この本の造本はとても凝っているのだけれど、ちょっと気になるところもあったりする。原著と比較してみたいところ。